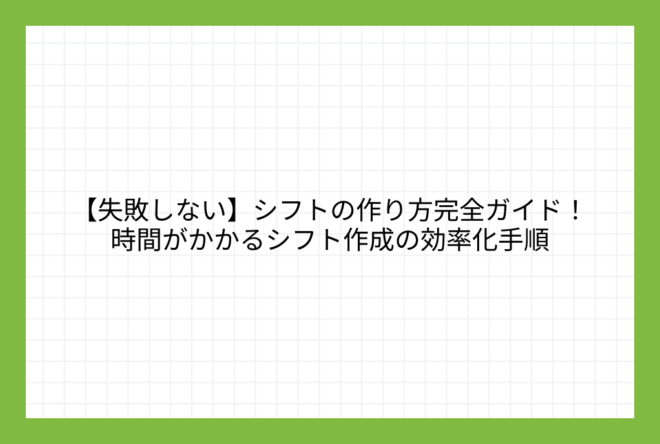シフト作成を担当されている皆様、毎月の作業でこのような悩みを抱えていませんか?
手間がかかりすぎる: 従業員の希望を集計し、複雑な条件を考慮するうちに時間がかかり、残業になってしまう。
ミスの多発: 勤務時間や連勤日数の計算ミス、または法令違反に気づかず後から手直しが発生する。
不公平感: 特定のスタッフに負担が偏り、不満や離職の原因になっていないか不安。
上記に思い当たる方は、「場当たり的」な作り方から脱却し、「体系的で効率の良いノウハウ」を求めているはずです。
本記事では、時間がかかるシフト作成を劇的に改善する「効率化のための7つの手順」を完全ガイドとして解説します。この手順を実践し、法令遵守と公平性を両立させることで、作成時間を劇的に短縮しましょう。
シフト作成前に必須!失敗を避けるための事前準備
シフト作成の失敗の多くは、作り始める前の準備不足に起因します。効率的な作成プロセスを確保するために、必ず以下の3点を明確にしましょう。
準備1:時間帯別の「必要人員数」を算出する
「だいたい○人いれば大丈夫」という曖昧な判断は、人件費のムダや人員不足の原因になります。
効率化のコツ
30分単位または1時間単位で、過去の売上データや予約数に基づき、必要なスタッフ数(スキルレベル含む)を算出し、シフト表の最上段に明記します。- よくある失敗
必要人数を把握していないと、ピークタイムに人が足りずスタッフの疲弊を招くか、逆にアイドルタイムに人が多すぎて人件費が無駄に発生します。この失敗を防ぐためには、データに基づいた明確な基準設定が不可欠です。
準備2:守るべき「制約条件」の優先順位を決める
希望シフト、スキル、資格、法令など、多くの条件が矛盾するときに備えて、「何が最優先か」を決めます。
優先順位の例
1. 法令遵守 → 2. 必須資格の配置 → 3. 必要人員数の充足 → 4. 従業員の希望- よくある失敗
優先順位があいまいだと、特定スタッフの希望を優先した結果、必要な資格者が配置できず営業に支障をきたす、あるいは法令違反のリスクを負う、といった判断ミスが生じます。
準備3:法令遵守のための「ルール」をチェックする
手動でのチェックでミスしやすい法定ルールを事前に確認し、チェックリストとして手元に用意しておくことが、手戻り時間を減らす鍵です。
重要チェック項目
労働時間・休憩: 6時間超で45分、8時間超で1時間の休憩付与。
休日: 原則として毎週1日、または4週間を通じて4日以上の休日付与。
連勤: 労働基準法上の制限だけでなく、社内の連勤制限ルールを確認。
- よくある失敗
特に休憩時間の付与と連勤日数の確認が甘いと、シフト確定後に労務担当者から指摘が入り、全員のシフトを組み直すという最大のムダが発生します。
【実践編】時間がかかる作成を効率化する7つの手順
事前準備が終わったら、以下の手順に従ってシフトを作成することで、ムダな手戻りをなくし、作成時間を大幅に短縮できます。
| ステップ | 作業内容 | 効率化のコツ(時短ノウハウ) |
| Step 1 | フォーマットを用意し、基本情報を入力する | 前月のフォーマットを再利用するなどして、スタッフの氏名・契約時間、必要人員数、制約条件などを入力する「たたき台」を準備する。 |
| Step 2 | 絶対に動かせない「固定シフト」を配置 | 正社員や固定勤務のパートなど、動かせない枠を最初に埋める。これにより、調整が必要な残りの枠が明確になります。 |
| Step 3 | 必須資格・スキルを持つスタッフを優先配置 | 資格保有者や熟練スタッフを、必ず必要な時間帯(例:オープン、クローズ、ピーク時)に先に配置する。 |
| Step 4 | 従業員の「希望休」を全て反映する | 希望休を全て反映した後、「希望が通らなかった日」をマークアップし、公平性の判断材料にする。 |
| Step 5 | 不足している枠を埋める(調整の核心) | 「人員が不足している日」と「希望が通らなかったスタッフ」を突き合わせ、公平性を考慮しながら勤務日を割り当てていく。 |
| Step 6 | 法令・条件を最終チェックする | 作成完了後、準備段階で作成したチェックリスト(連勤、休憩など)に基づき、全員分を上から下まで再確認し、ミスがないか検証する。 |
| Step 7 | フィードバックを得て、速やかに共有する | 確定前に、特に調整が難しかったスタッフやリーダーに確認してもらう。確定後は、速やかに共有(掲示、メールなど)する。 |
【補足】Step 1で入力する「基本情報」とは?
ここで入力する「基本情報」とは、シフト作成の土台となる「変動しない情報」と「事前に確定した条件」を指します。具体的には、以下の3点です。
- スタッフの契約情報
氏名、ID、契約上の最大労働時間や最低勤務日数など、法令や契約で定められた制約。 - 現場の必須要件
準備1で算出した、日別・時間帯別の必要人員数と、各スタッフの保有スキル・資格。 - 現場のルール連勤上限や休憩時間など、準備2・準備3で明確にした優先度の高い制約条件。
この基本情報を正確にセットすることで、後のStepでの調整をスムーズに進めることができます。
特に難易度が高いのはStep 5「不足している枠を埋める」
シフト作成で最も時間がかかり、担当者の経験と判断が問われるのがこのStep 5です。
Step 4までに固定枠と希望休を反映した結果、必ず「人員が不足している時間帯」と「希望通りにならなかったスタッフ」が残ります。この段階では、公平性を保ちつつ、すべての制約条件を満たす「最適解」を人の手で探索する必要があり、ここで費やす時間がシフト作成時間の大部分を占めます。この難易度の高さこそが、自動作成システム導入の最大の動機となります。
Step 5「不足している枠を埋める」でよくあるトラブル
この最も難しい調整段階で、手戻りやスタッフの不満に繋がるトラブルは以下の2点に集約されます。
トラブル1:特定スタッフへの負担集中
人員不足の日や人気の高い時間帯(週末など)のシフトを、依頼しやすい特定のスタッフに集中させてしまい、不公平感や疲弊を招く。トラブル2:法令違反の見落とし
不足を埋めることに集中するあまり、急遽追加したシフトが、連勤上限や月間の労働時間上限を超過し、Step 6の最終チェックでやり直しとなる。
Step 5の解決策は「調整の透明性と記録を徹底する」
トラブルを回避し、効率的に調整を完了させるためには、公平性を担保する記録と判断基準の透明性が不可欠です。
解決策1:過去の貢献度を可視化
全員の過去1〜2ヶ月間の週末勤務回数や、希望が通らなかった回数をリスト化し、調整の根拠とします。貢献度の低いスタッフから優先して不足枠を埋めるようにします。
- メリット: 公平性の根拠をスタッフに示せるため、不満を大幅に軽減できます。
- デメリット: 貢献度のリスト化自体に初期の手間がかかります。(※シフト自動化ツール導入で解消可能)
解決策2:制約条件をメモに残す
シフトを埋める際、「Aさんはすでに今週4日勤務」「Bさんは〇〇時間までOK」など、制約条件を手元のメモやExcelの備考欄に都度記録することで、法令違反をリアルタイムで防ぎ、手戻りを最小化します。
- メリット: リアルタイムで法令違反のリスクを把握でき、手戻りのリスクをほぼゼロにできます。
- デメリット: 調整中にメモの記録・確認を常に意識する必要があり、集中力を要します。
【課題別】シフト作成ノウハウの具体的なヒント
作成手順をマスターしても、シフト作成の根本的な課題である「人員不足」や「不公平感」が解決しない限り、毎月の負担は続きます。ここでは、これらの恒常的な課題を解決するためのノウハウを解説します。
【課題1】 人員不足を恒常的に回避したい場合
人員不足は、シフト調整の難易度を上げる最大の要因です。シフトを組む努力だけでなく、事前にスタッフの協力を得るための「仕組み」を導入することが根本的な解決策となります。
シフトが確定してからではなく、希望収集の段階で「不足しそうな日」をスタッフにアナウンスし、協力を依頼しましょう。
特定のスタッフに負担が偏らないよう、全員のスキルアップを進め、代わりがきく体制を整えることが根本的な解決策です。
【課題2】従業員間の不公平感をなくしたい場合
「なぜあの人だけ希望が通るのか」という不満は、人間関係の悪化や離職に直結します。調整の過程で生じた不公平感を「見える化」し、透明性を確保することが極めて重要です。
希望休が通る回数や、大変なピーク時間帯の勤務頻度を、全員分集計して比較できるリストを作成し、誰がどれだけ協力しているかを客観的に把握しましょう。
不公平が生じた場合は、「次回は必ず考慮する」ことを具体的に伝え、透明性を確保してください。
Excelやツールでシフト作成効率を格段に上げるテクニック
作成に使うツール(Excel、スプレッドシート、簡易アプリなど)に関わらず、以下のテクニックを使うことで、手動での計算ミスや確認作業の時間を劇的に減らせます。
①条件付き書式や機能で「視覚化」する
人間の目による確認には限界があります。システム的な「色付け」の仕組みを導入することで、調整が必要な部分を瞬時に特定し、確認時間を劇的に短縮できます。
時短ノウハウ
必要な人員数を下回った箇所や、連勤が続いている箇所など、調整が必要な部分に自動で色が付くように設定を行います。これにより、どこを調整すべきかが一目でわかり、確認時間を短縮できます。メリット
調整箇所や法令違反リスクを直感的に把握でき、シフト作成の判断スピードが向上します。デメリット
初期設定にExcelの関数知識が必要であり、複雑な条件設定には手間がかかります。
②関数や自動計算で「集計を自動化」する
月末の集計作業は、シフト作成後の最も大きな負担の一つです。勤務時間や人件費の計算を自動化することで、転記・集計ミスとそれに伴う手戻りの時間を完全にゼロにできます。
時短ノウハウ
各従業員の勤務時間合計や、特定の時間帯の合計出勤者数など、集計が必要な箇所には必ず計算式を設定します。勤務時間が入力されるだけで自動で合計されるため、手計算によるミスと時間がゼロになります。メリット
計算ミスのリスクをなくし、給与計算に向けたデータ準備の時間を大幅に短縮できます。デメリット
集計ルールが複雑な場合、関数の設計自体に大きな時間と専門知識が必要になります。
③入力規則で「ミスを防ぐ」
集計エラーの多くは、シフトの入力時に発生する「表記ゆれ」が原因です。あらかじめ入力できる値を限定することで、この根本的なエラーを未然に防ぎ、後の集計作業の負荷をなくします。
時短ノウハウ
シフト表に入力できる値を「早番」「遅番」「休み」など事前に設定しておく(入力規則)。これにより、誤字脱字による集計エラーを未然に防ぐことができます。メリット
集計時のエラーチェックや修正作業が不要になり、最終確認の手間を削減できます。デメリット
勤務パターンが頻繁に変わる場合、入力規則の設定を毎回更新する手間が発生します。
シフト作成システムの導入を検討したいタイミング
上記で解説した効率化の手順やExcelテクニックを実践してもなお、以下のような課題が残る場合は、システム導入を検討する最適なタイミングです。手動での限界を認識し、次のステップに進むことで、真の効率化が実現します。
- 作成時間が「月に8時間」を超えている
毎月、丸一日以上の時間を作成に費やしている場合、その人件費と機会損失を考慮すると、システムの月額費用が十分に回収可能です。 - 月末の「集計・転記ミス」が頻繁に起こる
給与計算の直前でミスが発覚し、修正に追われている場合、法令リスク回避のためにも、自動集計・連携機能を持つシステムへの移行が必須です。 - 「複雑な制約条件」が人手を介さずクリアできない
複数の資格、複雑な連勤ルール、人件費予算など、多くの制約を同時にクリアする「最適解」の探索に疲弊している場合、AIや高度な自動作成機能を持つシステムの出番です。
まとめ:ノウハウ実践の次へ!システムの導入で「時間」を戦略資産に
本記事で解説した手順とノウハウを実践することで、シフト作成のムダな時間は確実に削減できます。しかし、「複雑な条件調整」「月末の集計・転記ミス」「不公平感の解消」といった根本的な課題は、手動には限界があります。
もし、あなたが記事を読み、「もう手作業の限界だ」と感じたなら、それはシステム導入を検討する最適なサインです。
| 手動管理の限界 | システム導入による解決 |
| 複雑な調整時間 | AI/自動作成機能で、法令・公平性をクリアした最適解を数分で生成。 |
| 集計・転記ミス | 勤怠・給与システムと自動連携し、月末のミスと手間を完全にゼロに。 |
| 不公平感 | 過去の勤務状況や希望の可否をシステムが記録・反映し、公平性を担保。 |
低コストで確かな自動化効果を得たい場合は、SHIFTEE(シフティー)などのシステムが有力候補です。月額250円(税抜)/名程度から集計・転記のムダを解消できる上に、必要に応じてAI機能を追加できる柔軟性も備えており、低予算で業務改善の第一歩を踏み出せます。(※ただし、別途サーバー発行料50,000円(税抜)がかかります)
勤務表の自動作成システムは、担当者を重労働から解放し、本来注力すべき店舗運営や戦略的な業務に「時間」という貴重な資産を振り分けるための、最も効果的な投資です。ぜひ、本記事を参考に、導入検討を進めてください。